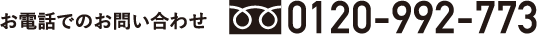古民家の再生のポイントとは!?
建て替えかリノベーションかの見極め
浜松市と隣接エリアに点在する古民家は、伝統工法ならではの歴史的にも価値のある建物が多いです。一方で、現行の耐震基準では認められていない束石に建物を載せてあるだけ基礎だったり、中には建物が傾いているケースも少なくありません。Remoreでは数多くの築古戸建のリノベーションに取り組んできた知識、経験を活かし、基礎の状態や構造上の問題から、建て替えか、リノベーションかプロの視点で最適な判断をします。

1981年の建物は現行の耐震基準が制定される前になりますので、地震に弱い建物が多いと言われています。Remoreでは、耐震診断を実施し、診断結果をもとに基礎補強工事も含めたベストな耐震設計を行います。施工段階では、設計プランに基づいた施工を徹底します。


古民家の多くは、夏季の気温を想定して建てられています。したがって、現行基準を満たしている建物に比べると、断熱性能、気密性能が低く、多くは断熱材が入っていない無断熱の状況です。Remoreでは、床、壁、天井に断熱材を充填し、窓も高性能サッシに交換することにより、冬は暖かく、夏は涼しい快適な建物に生まれ変わります。
伝統工法の古民家の場合、鴨居や梁に大きな木材が使われていることがよくあります。「差鴨居」という鴨居ですが、この差鴨居を入れることで両側の柱と接合されている梁とでH型の加工ができ、これが強度的にも大変有利になるからです。また、ダイナミックに露出させる梁は古民家リノベーションならではの魅力です。
Remoreなら、大きな腐朽、劣化がなければ伝統工法の構造材を活かしながら、構造面、デザイン面という複眼的な視点から最適な提案をします。昭和のレトロとRemoreの技術の融合は古民家リノベーションの大きな醍醐味の一つです。

- 古き良き日本の原風景を思わせる佇まいで街の景観としての役割も担っている
- 夏は涼しく過ごせるよう、先人の知恵が建物に詰まっている
- 古民家の多くが地震の力を逃がす免震的な構造という考え方で建設されている
- 地域材を積極的に採用し、地方創生、循環型社会という考え方がベースになっている
- 珪藻土や漆喰(しっくい)など自然素材中心で健康に優しい
- 古民家リノベーションは価値ある柱、梁、欄間などを活かしながら、現代の性能やデザインとの融合が実現できる
- 無断熱の状態が多く、断熱性能は総じて低い(リノベーションにより解決可能)
- 耐震性能はファジーな部分があり、会社ごとの考え方によるところがある(今後、法的に規定される可能性あり)
- 築年数が古ければ古いほど、高度な耐震改修ノウハウが求められ、リノベーションの難易度が高くなるため、対応できる会社が限られる






古民家には大きく3タイプがあると言われています。

農村民家
山間部などに見られる古民家で、農家住宅とも言われます。土間には煮炊きするかまどがあり、縁側や屋根裏で作業スペースがあったりします。住まいとお茶をはじめ地域産業との結びつきがある間取りになっていることが特徴です。

商家民家
古くは江戸時代の宿場町や問屋町など道路に面して商店が密集した古い街並みが特徴です。商店スペースの裏側が住まいのスペースになっていたりします。行政と連携した街づくりを目的としたリノベーションにより再生されるケースが増えています。

武家民家(武家屋敷)
武家が所有した邸宅を言います。大名レベルの邸宅は大名屋敷、藩邸と言ったりします。武家造りとも言われて、武家の生活様式に合わせている他、防衛のための造りになっている点が特徴です。
古民家は、そこに住む人より長くその街に存在する貴重な建築文化です。非常に価値のある柱、梁(はり)も豊富で、多くの思い出も詰まっています。当社では、建築のプロ集団の衆知を結集して、住み継ぐ人の思いに寄り添いながら、古民家リノベーションに取り組んで参ります。










 お問い合わせ・来場予約
お問い合わせ・来場予約